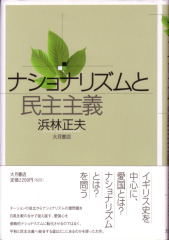
浜林正夫先生の新著『ナショナリズムと民主主義』を早速読み終えました。
本書は、イギリス(正確にはブリテン)史にそって、ナショナリズム(同じ国家に帰属しているという意識)がどのように成立、展開してきたかをたどったものです。

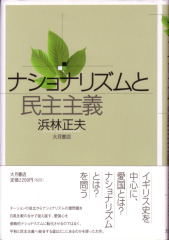
浜林正夫先生の新著『ナショナリズムと民主主義』を早速読み終えました。
本書は、イギリス(正確にはブリテン)史にそって、ナショナリズム(同じ国家に帰属しているという意識)がどのように成立、展開してきたかをたどったものです。

「維新史を書き直す意欲作」という宣伝文句。もちろん、この間の資料発掘や研究によって明らかになった新事実をもりこんだ最新の通史という意味で、僕自身、いろいろ勉強にもなったし、なるほど考えなおさないといけないなと思ったところもたくさんあります。

2006年ノーベル文学賞を受賞したオルハン・パムクの『雪』です。
以前から、「トルコの小説って、珍しいなぁ…」と思って気にはなっていたのですが、ノーベル賞をとったということで、読んでみることにしました。(^_^;)←けっこうミーハー
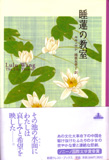
おまつり本番でヘロヘロモードのなか、電車の行き帰りでルル・ワン『睡蓮の教室』(新潮社)を読んでいます。
続きを読む

植村邦彦氏の新著『マルクスのアクチュアリティ――マルクスを再読する意味』(新泉社、10月刊)を読み終える。2日ほど、通勤の行き帰りの電車の中で読んだが、とくにひっかかるところもなく、軽く読めてしまったというのが率直な感想。

晩飯の材料を買いに駅前のスーパーへ行ったとき、たまたま近所の本屋さんを覗いたら、新刊書のところにこの本が並んでしました。
コバケンさんの語り下ろしたような文章と、可愛らしいイラストで、オーケストラとクラシック音楽(といってもオーケストラで演奏する交響曲などに限定されますが)の魅力と楽しみ方が紹介されています。
【書誌情報】書名:小林研一郎とオーケストラへ行こう/著者:小林研一郎/出版社:旬報社/発行:2006年10月刊/定価:1600円+税/ISBN4-8451-0993-X
9月に買った本です。今月はあまりたくさん買わなかった……かな?

仙台出張の行き帰りで、こないだから読んでいたクリストフ・コッホ『意識の探求』(上下、岩波書店、6月刊)を読み終えました。
続きを読む

8月の集英社新書で、作家の加賀乙彦さんがこんな本を出していたので、思わず買ってしまいました。(^_^;)
続きを読む
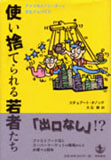
『ニッケル・アンド・ダイムド』に続けて、アメリカの下流労働者の実態を取り上げた本です。取り上げられているのは、米国の大都市「ボックスヒル」のスーパーマーケットとカナダの大都市「グレンウッド」のファーストフード店で働く若者たちです。
この間読んだ雑誌記事について。
ということで、最近買った本をリストアップしておきます。

『日本通史<III> 国際政治家の近代日本』の宮地正人氏が解題を書いているということで、2001年に再刊された井上清『日本現代史<I> 明治維新』(東大出版会、親本は1951年刊)を手に入れて読みました。大学に入ったばかりのころに読んだ記憶はあるのですが、内容はまったく忘れてしまっていました。(^^;)
続きを読む