2日の広島・巨人戦(広島球場)を、フジテレビは生中継しませんでした。曰く、「レギュラー番組のニーズが高い」「5位6位の対戦でペナントレースに影響ない」とのこと。とりあえず、フジテレビに拍手喝采!
「文化」カテゴリーアーカイブ
まつもと泉、復活へ!
80年代に「きまぐれオレンジ★ロード」で一世を風靡した漫画家の まつもと泉さんが、近々復活か!?
体調不良で6年前から休筆状態でしたが、それが「脳脊髄液減少症」という難病であったことが判明。半分程度、体調が回復したとのこと。楽しみですね?
舘野泉さんの手記
ピアニストの舘野泉さんが共産党の「しんぶん赤旗」に手記を連載されています(初回7月28日、毎週木曜日掲載、これまでに6回掲載)。
「輝く音を求めて」というこの手記は、2002年1月に脳溢血で倒れたときに「騒然となった会場の雰囲気は良く覚えている」という話から始まり、意識が戻ったとき、声も出ない、身体も動かない、しかし頭の中では「フランスの作曲家、デオダ・ド・セヴラックの曲」が鳴り続けていたこと、記憶力も打撃を受け、「世の中とは断絶して、ただ自分をどうにか支えていくのに精一杯であった」と、率直に書かれています。
さらに、退院してから2度目にやってきた医師が、興味なさそうに塗り薬を出したのに「はらわたが煮えくりかえって、薬は使いもせず捨ててしまった」という話や、いろいろの人から見舞いをうけ、うれしいと思う半面、「これでピアニストとしての彼の人生も終わりだなと思う気持ちが見えてつらかった」ことまで、かなりあからさまに書かれてもいます。しかし、それが本当に正直な気持ちだったのだろうと思います。8月に地元の音楽祭の最終日に、飛び入り出演でピアノを弾いたこと、そのとき「聴衆は水を打ったように静まりかえり、すすり泣きの声も漏れてきた」こと、そして「人前で弾くのはこれが最後だなと思った」と言う話は、今だからこそそんなこともあったのかと思って読めますが、その時は、聴衆にとっても本当にこれが最後だと思えるつらい出来事だったに違いありません。
続きを読む
musical baton
「壊れる前に」のウニさんから、ミュージカル・バトンをいただいたところで、自宅のPCが壊れたため、すっかり遅れてしまいました。
●コンピュータに入っている音楽ファイルの容量
1.29G。これって多いのか少ないのか、どっちなんでしょう? この前、遅ればせながらmp3プレーヤーを買ったので、あれこれCDを読み込ませてみたのですが、<1>音質が悪すぎる、<2>メモリが1Gしかなく、頻繁にファイルを入れ替えないといけないので面倒。ということで、結局、またMDに戻ってしまいました。(^^;) したがって、HDD内の音楽ファイルは増えそうにありません。
●最後に買ったCD
ムラヴィンスキー指揮、レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団/チャイコフスキー:交響曲第4番、第5番、第6番《悲壮》(UCCG-3312/4)――1960年にロンドンとウィーンで録音されたムラヴィンスキーの銘盤。演奏はもちろんですが、西側で録音されたため、ムラヴィンスキーのCDとしてはめずらしく、音質が非常にいい。チャイコフスキーの曲はどうしても甘くなりがちですが、こんな渋い演奏もあるのだということを知り、感動してます。
●今聞いている曲
現瞬間は、音楽は聴いてませんが、今日聴いたのは、同じくムラヴィンスキー指揮、レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団/ショスタコーヴィッチ:交響曲第10番(1976年3月、レニングラード・フィルハーモニー大ホールで録音)。このCDは、クラシック音楽を聴き始めた最初の頃に買ったもの。録音には不満がありますが、演奏はピカイチです。
●よく聞く、または特別な思い入れのある5曲
う〜む、5曲と言われると、難しい…。ということで、こだわりのある演奏を5つ上げたいと思います。
- ギュンター・ヴァント指揮、北ドイツ放送交響楽団/ブルックナー:交響曲第9番――2000年11月のヴァント最後の来日コンサートのライブ録音。チケットはとっくに売り切れていたのですが、たまたまネットで知り合った人に貴重な1枚を譲っていただき、1晩だけ聞きに行くことができました。
- ピエール・ブーレーズ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団/ブルックナー:交響曲第8番――朝比奈隆、ギュンター・ヴァントとはまた違ったブルックナーを初めて知った1枚。ブーレーズのマーラー・シリーズも必聴のCDです。
- ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団/ベートーヴェン:交響曲第5番《運命》――1947年、フルトヴェングラーがドイツ国内復帰をはたした最初の演奏会という、言わずもがなの超有名な歴史的銘盤。60年近く前の演奏ですが、いま聴いてもものすごく新鮮で情熱的。もともと《運命》という曲自体あれこれやるとあざとくなる作品ですが、この演奏は、余計な脚色はいっさい排しつつ、しかし、自ずと内側から沸き上がってくるものに突き動かされるような感動を味わわせてくれます。
- 内田光子/シューベルト:ピアノ・ソナタ集――シューベルトのピアノ・ソナタ、即興曲などCD8枚にわたるチクルス。内田光子という演奏家を初めて知り、シューベルトのピアノ曲というものがこんなに奥深いことも初めて知ったCD集。それまで、もっぱら交響曲や協奏曲しか聴かなかったので、一気に音楽の世界がひろがった感じでした。
- フィリップ・ヘレベッヘ指揮、コレギウム・ヴォカーレ/J.S.バッハ:マタイ受難曲――それまでバッハは全く聴いたことがなかったし、そもそも第9やマーラーの交響曲を除けば、《歌》の入る曲はどちらかというと嫌いだったのが、まったく一変させられました。これを聴いてから、バッハ・コレギウム・ジャパンの公演やミシェル・コルボの来日公演など、すっかりバッハの受難曲に魅せられています。
ということで全部クラシックになりましたが、たまには他のジャンルの音楽も聴くので、クラシック以外から2枚だけ上げておきます。
- キース・ジャレット:ケルン・コンサート――大学4年のときに、友人がテープに録音してくれて、初めて聴いたキースのアルバム。他にもキースのアルバムはたくさん持っていますが、やっぱり一番こだわりがあるのはこれ。
- 中森明菜:歌姫<スペシャル・エディション>――酒やら何やらで、ボロボロになってしまった感のある中森明菜ですが、歌わせたら、山口百恵に次ぐのは、やっぱり彼女をおいて他にないでしょう。(^^;)
ということで、本当なら最後にバトンを渡す人を5人上げないとダメなんですが、そういう相手もおらず、僕のところに届いたバトンはこれにて打ち止め…ということにしたいと思います。お許しください。
今年の絶対見るべきでない映画第1位!
予告編を見たときは、設定のセンスがいいと思って、わざわざ渋谷まで見に行ったのですが、結果は、今年の絶対見るべきでない映画第1位に見事当選! 隣に座った欧米系外国人女性(英語喋ってたからたぶんアメリカ人だろうけど)が途中で席を立っていったのは、ある意味、正解だったかも。(今年19本目)
続きを読む
吉永小百合さんの思い
今日の「東京新聞」夕刊、「あの人に迫る」というコーナーで、俳優の吉永小百合さんが、「声が出るかぎりは続けていきたい」と原爆詩の朗読を続ける思いを語っていられます。
改憲の動きについて
憲法9条が私たちを守ってくれていると思うんですね。60年間、外国に行って人を殺さなかったというのは日本の誇りだと思うし、よその国からうらやましがられている憲法だと思うんですね。それを大事にしないって言うのは分からないし。すぐ(改憲論者は)国際貢献のためには、っておっしゃるけど、武力じゃなきゃ国際貢献は成立しないのって聞きたくなるんですね。言葉や頭を使ってできるはずです。
ときっぱり。さらに、最近の日本の動きについても
続きを読む
都響創立40周年記念コンサート:ヴェルディ「レクイエム」
去る7月29日(金)と30日(土)、東京都交響楽団創立40周年記念2日連続コンサート「〈レクイエム〉から〈歓喜〉へ」が催されました。その初日、ヴェルディ「レクイエム」の演奏会に行ってきました。
第1曲「レクイエムとキリエ」が始まったときは、ちょっと遅いかな?と思ったのですが、それは最初だけでした。ソロは、なんといってもメゾソプラノの竹本節子さんが声量といい、声の艶といい、ダントツで良かったと思いました。ソプラノの中村智子さんは、第7曲の最後になって、急に声が出なくなっていました。声こそ割れなかったものの、ラストの盛り上がりがちょっと損なわれてしまい、残念でした。
う〜ん、ベタすぎる…
ちょっと気分転換に

ひきつづき、永原慶二先生の本を読んでいます。ようやく『日本封建制成立過程の研究』(1961年)の半分ぐらいまでさしかかりました。
で、気分転換に、河島みどり『ムラヴィンスキーと私』(草思社)を読み始めました。表紙や扉の、ムラヴィンスキーの凛々しい写真に、思わず買ってしまったものです。
ほんとにまだ読み始めたばかりなのですが、ムラヴィンスキーの父の異母妹(つまり、ムラヴィンスキーの叔母さんは、あの革命家アレクサンドラ・コロンタイだったんです! むむ、知らんかった…。
【書誌情報】著者:河島みどり/書名:ムラヴィンスキーと私/出版社:草思社/出版年:2005年5月/定価:本体2000円+税/ISBN4-7942-1398-0
ペンデレツキ「ヒロシマの犠牲者に捧げる哀歌」
映画「トーク・トゥ・ハー」にこの曲が登場することに関連して、何かの雑誌に、どこかの誰かが書いていたという話(読売日響第440回定期演奏会 スクリャービン交響曲第5番「プロメテウス―火の詩」)を載せたところ、友人のD井君から、それは『平和運動』7月号に載った尾崎明「犠牲の意味について――ペンデレツキ『ヒロシマの犠牲者に捧げる哀歌』」では?とのメールをいただきました。
その通りです。ご指摘、ありがとうございました。m(_’_)m
それを読むと、この曲について、こんなふうに書かれています。
読売日響第440回定期演奏会 スクリャービン交響曲第5番「プロメテウス―火の詩」
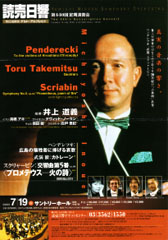
今日は、井上道義氏が振るというので、読売日響の定期演奏会に行ってきました。
読響の演奏会は、確か2度目? 客層などが、ビミョーに日フィルや都響と違うのがおもしろかったです。(^_^;)
プログラムは以下の通り。
- ペンデレツキ:広島の犠牲者に捧げる哀歌
- 武満徹:カトレーン
- 休憩
- スクリャービン:交響曲第5番 “プロメテウス―火の詩”
最近、何かの雑誌で、どこかの誰かが映画「トーク・トゥ・ハー」にふれて、映画の中で、コーマとなった若い女性(アリシア)に、バレエの先生が「広島の犠牲者に捧げる哀歌」を聴かせるシーンが出てくることを書いていました。僕がはじめてペンデレツキという名前を知ったのも、「広島の犠牲者に捧げる哀歌」(の一部)を聴いたのも、この映画でしたが、その印象は強烈でした。
ということで、今日はぜひこの曲をナマで聴きたいと思ってやってきました。
元気でね、Dear フランキー

投稿の順番が前後してしまいましたが、先々週、渋谷Bunkamuraル・シネマで映画「Dear フランキー」を見てきました。(今年17本目)
舞台はスコットランド。台詞は、スコットランド風英語で、最初、映画が始まったときは、いったい何語?と思ってしまったほどです(まあ、僕の語学力が乏しいせいですが)。
難聴の少年フランキー(ジャック・マケルホーン)を育てるシングルマザーのリジー(エミリー・モーティマー)、それにリジーの母親ネルの3人家族は、何度目かの引っ越しの様子。貧しいながら、毎日、新聞の死亡欄や尋ね人の欄を確かめるネル。フランキーは、船乗りの父親にあてて手紙を書くのが楽しみで、父親からは、寄港先の珍しい切手が送られてくる。しかし、その手紙は、実は母親のリジーが、フランキーに寂しい思いをさせないために、書いていたものだった。そんなある日、地元の新聞に、父親の乗った船が入港する、という記事が載り、フランキーとクラスメートとは、父親が会いに来るかどうかで賭けをすることに。それを知ったリジーは、1日だけの父親役を捜すことに…。
修復されたら早く見たいなぁ
岡本太郎の幻の壁画「明日の神話」の修復作業がいよいよ始まりました! 無事に修復されたら、ぜひ早く見たいものです。
岡本太郎壁画:「明日の神話」、修復へ35年ぶり里帰り(毎日新聞)
こちらは、岡本太郎記念館の「原画」です。
描かれたものと描かれなかったもの ヒトラー?最期の12日間
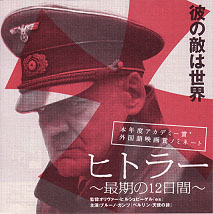
話題の映画「ヒトラー?最期の12日間?」を見てきました(渋谷・シネマライズ)。実を言うと、日曜日(7/10)にも見に行ったのですが(シネマライズは、日曜最終回はいつでも1000円!)、満員・立ち見で、あきらめて帰ってきました。今日は、約8割のお客さんというところでしょうか。普段、シネマライズでは見かけないような年配のお客さんも見かけましたが、やっぱり圧倒的に多いのは若いお客さんでした。(今年18本目の映画)
さて、見た感想ですが、圧倒的としか言いようのない作品でした。とくに、これでもかこれでもかと描かれる、ソ連軍の砲撃を次々に打ち込まれていくベルリンの街の様子からは、本当に戦争というもののもつ残虐さ、残酷さが伝わってきます。
また、安全な地下壕の中で、最期の作戦指揮をとろうとするヒトラーには“狂気”すら感じさせられます。そして、ヒトラーを取り巻く将校連中は、みんな、帝国の「最期」を目前に、どこかでヒトラーに引導を渡さなければいけないと思っているにもかかわらず、裏切り者として処刑されることを恐れ最期まで忠誠を尽くそうとする者と、何とか脱出して生き延びることを考える者との間で、無駄な当てこすりやかけひきに時間が空費されていく…。そこには、「国民」を守ることなどまったく登場せず、ヒトラーの狂気は、そのまま「第三帝国」の狂気を示していると思いました。
その狂気を浮き彫りにしてくれるのは、1人の軍医の冷静な目と、狂信的なヒトラーユーゲントの少年です。(プログラムや公式ホームページでは、この2人の俳優が誰なのか書かれてないのが残念です)
しかし他方で、この映画では、ヒトラーとナチスが何をやったかは、まったく描かれません。映画は、主人公のユンゲがヒトラーの秘書に採用された1942年11月から、いきなりベルリン陥落目前の1945年4月20日に飛ぶので、その間に起こったことは、すっぽり抜け落ちています。
日フィル第572回定期/ヴェルディ:レクイエム
金曜日、締め切り最終日の仕事をそそくさを終わらせて、日フィル定期演奏会に行ってきました。
- ヴェルディ:レクイエム
ヴェルディのレクイエムは、レクイエムなどといいながら、超ど派手な曲。それを、炎のコバケンがいったいどう料理するのか? 興味津々でサントリーホールに向かいました。
アイデアは最高 「メリンダとメリンダ」

少し前に、恵比寿ガーデンシネマで見てきた映画です。(今年16本目)
こっちのメリンダ(ラダ・ミッチェル)は、裕福な医者と結婚して子どもも2人いて、幸せだったはずなのに、カメラマンと浮気した挙げ句に捨てられ、自殺未遂をして精神病院に収容されていたというボロボロな状態。他方、もう一人のミランダ(やっぱりラダ・ミッチェル)も、裕福な医師と離婚したけれど、こっちはさっさと次の恋を探しに行くという感じで、どちらも友人宅のパーティーに突然転がり込み、ピアニストと出会うというところは同じ。それなのに、不幸なメリンダと幸福なメリンダでは、こんなに結末が違ってしまう…という作品です。しかも、それを一人の女優に二役で演じさせるというところも、映画の作り方として興味あります。
個人的な好みからいえば、不幸な方のメリンダのストーリーの方が見ていて面白いですね。ちょっと崩れた感じで、感情の起伏を押さえきれないあたりも危なっかしい。いわゆる破滅型なんでしょう。実際の恋人がこんなのだったら迷惑きわまりない話ですが、見てる分にはハラハラ、ドキドキ、飽きさせてくれません。
ただし、(このあと、ややネタばれ、興ざめ的コメントあり)
シャラポワ、準決勝で敗退

早く寝なきゃと思いつつ、つい見てしまいました。
ビーナス・ウィリアムズが左右に振ってくるのにたいし、シャラポワの方はコーナーが微妙に外れたりネットに引っかかったり…。それでも、第1セットタイブレークまでは、なんとか踏みとどまっていたように見えましたが、第2セットは集中力が切れてしまったみたいでした。残念…。
それより、ダベンポート?モレスモ戦とシャラポワ?V・ウィリアムズ戦を同時に開始するとアナウンスされたときのお客の反応。最初はブーイングをしておいて、ダベンポート?モレスモ戦は第1コート、シャラポワ?ウィリアムズ戦をセンターコートでやると発表されると、とたんに拍手が沸いていました。それじゃあ、ダベンポートとモレスモに失礼じゃん…。まあ僕もテレビ観戦の理由はシャラポワだけどさぁ。(^_^;)
都響第611回定演Aシリーズ/メシアン:トゥランガリラ交響曲
選挙中で申し訳ないと思いつつ、それでも今季都響定演Aシリーズを選んだ目的の1つだったので、こっそり聴きに行ってきました。
- 原田節:「薄暮、光たゆたふ時」〜オンド・マルトノとオーケストラのための
- メシアン:トゥランガリラ交響曲
ということで、オール“オンド・マルトノ”プログラム。オンド・マルトノと言われても、僕は分からなかったのですが、鍵盤付きだけど、中間音も出るという不思議な電子楽器です。「宇宙大作戦」(スター・トレック)のテーマ曲のタ〜リ〜〜〜ラリ〜〜〜という、あんな感じの音といえばピンとくるかも(ただし、ほんとにあの曲がオンド・マルトノかどうかは知らないけど)。
訃報:元阪神タイガース遠井吾郎選手…
僕にとっては、田淵幸一、藤田平、ラインバック、ブリーデンなどとともに70年代の阪神タイガースの代表選手でした。まあ、最後は代打ばかりで、遠井がファーストの守備につくと、1塁方面に飛んだゴロはみんなヒットになると言われてましたが…。合掌
これで15歳… ミシェル・ウィー

ゴルフの全米女子オープン。15歳のミシェル・ウィーは、最終日、2バーディ7ボギー3ダブルボギーと大崩れしてしまいました。それにしても15歳で身長183センチ、長??い手足からのショットは強力です。

