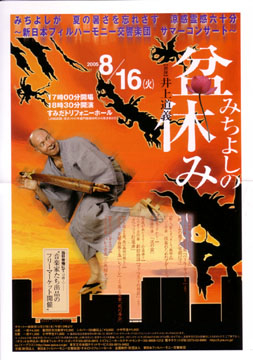「ピアノマン」の登場ですっかり手垢が付いてしまった感がありますが、渋谷Bunkamuraル・シネマで、ジュディ・デンチとマギー・スミスが主演するイギリス映画「ラヴェンダーの咲く庭で」を見てきました。(ことし15本目)
イギリスの海辺の片田舎に住むジャネット(マギー・スミス)とアーシュラ(ジュディ・デンチ)の姉妹。嵐の翌朝、若い男性(ダニエル・ブリュール)が浜辺に打ち上げられているのを見つける。若者は英語がはなせないけれども、ドイツ語でポーランド出身でアンドレアと名のる。アーシュラは、そんなアンドレアをかいがいしく世話する。回復したアンドレアは見事なヴァイオリンの腕前を発揮する。
そんなある日、アンドレアの演奏を聴いた若い女性画家オルガ(ナターシャ・マケルホーン)が登場。オルガの兄は伝説の名ヴァイオリニスト。アーシュラとジャネットは、アンドレアとドイツ語で親しげに会話するオルガに心中穏やかでない…。