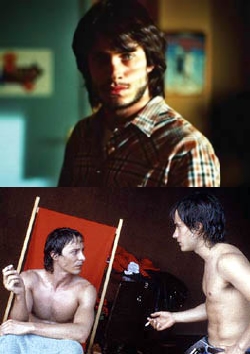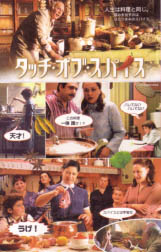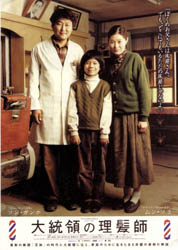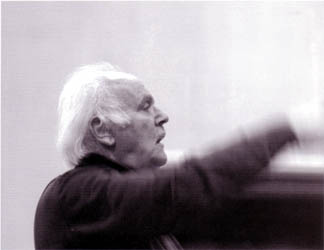12日にひらかれた日本ペンクラブの緊急集会「いま、戦争と平和を考える」には400人を超す聴衆が集まったけれど、一般紙の報道はベタ記事扱い。しかし、今日の「東京新聞」夕刊は、文化欄で、それを詳しく報道しています。
阿刀田高氏
もし日本が攻撃されたらとの仮定で語った阿刀田氏。「憲法のいう『諸国民の公正と信義』を信じていたら、変なのが来たらやられる。それは分かっている。でも私たちは戦争は悲惨であるとつくづく分かったのでこの憲法をつくった」。憲法が時代遅れと言われ、改憲論が強まる中で、敗戦後の憲法制定の初心に立ち返るよう呼びかけた。
「平和憲法は、命を捨てても守っていいほど価値がある」とも言う同氏だが、それは他国の脅威を座して待つ姿勢ではない。「攻撃されないための外交努力は、とことんやってほしい」と、武力によらない政策展開をうながした。
吉岡忍氏
政治家たちの言葉の危うさについては、吉岡忍氏も米中枢同時テロ以降のブッシュ米大統領と小泉首相の発言録をもとに分析。「一読して分かるのは感情的、情緒的な言葉が多いこと。根拠のなさをごまかすためどんどん感情的になっていくのがよく分かる」
その根底にあるのは、すべてを単純化し、「善悪、白黒」といった二元論で割り切る態度だと同氏はみる。
辻井喬氏
辻井喬氏は「平和」の概念を考え直す問いを発した。「平和とは、戦争をしていない状態でしょうか? グローバリゼイションの浸透で、昔の平和とは中身が変わった。石油文明的な、あこがれの生活を過ごし、戦争がなければいいと満足していていいのか。私たちの平和は戦争をなくす方向に働きかける平和か、グローバリゼーションで追いやられる人たちがいつか爆発する契機となる平和か、検証する必要がある」
辻井氏はまた「平和が戦争を推進する方に乗じられるおそれがある。近くの国が核兵器を持つなら、私たちも平和のために核兵器を持つのか」との設問も示した。戦争と平和を問うことは、私たちの生き方そのものを問うこと。そう思わせる言葉だった。
ほかにも、ペンクラブ会長の井上ひさし氏や翻訳家の米原万里さん、アジ研の酒井啓子さんの発言なども紹介されています。文化欄のほとんど全部を費やしての報道、ほんとうにご苦労さまでした。