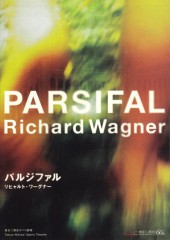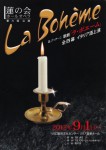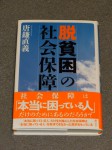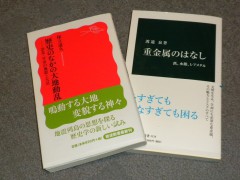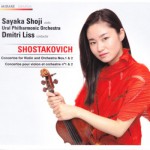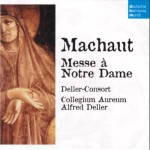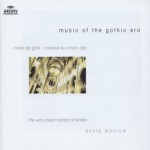先週の仙台出張のさい、はやてに乗りました。(^_^)v
マルクスの理論は僕たちが世界をつかみとるための「武器」だ
昨夜は、マルクスの理論を学ぶことの意味について、呟きました。
インバル=都響〈新〉マーラー・ツィクルス始動!
月曜日のパルジファルに続いて、昨晩も上野の文化会館へ。「インバル=都響〈新〉マーラー・ツィクルス」の第1弾、マーラー交響曲第1番を聞いてきました。
- マーラー:さすらう若人の歌
- マーラー:交響曲第1番 ニ長調 「巨人」
前半「さすらう若人の歌」のソロは、バリトン・小森輝彦さん。
二期会「パルジファル」
ですます調『資本論』。第1章第1節完了!
「です・ます」調での『資本論』翻訳の試み。第1章第1節の本文だけですが、完了しました。
やってみると、いわゆる翻訳調の堅苦しい文章のまま文末だけ「です・ます」にすることは不可能なので、全体を平易にせざるをえない。そこが面白いですね。
科学的社会主義の理論についてお話ししてきました
昨日は仙台まで出張して、科学的社会主義の理論についてごく基本的なところをお話ししてきました。
従軍慰安婦問題でアメリカ国内で「対日不信」
李明博大統領の「謝罪発言」、領土問題もからんで、アメリカで、日本の従軍慰安婦問題にたいする態度に「対日不信」が広まっているそうです。日本経済新聞ネット版のスペシャルリポートで、編集委員の春原剛氏が「従軍慰安婦問題 米国でも強まる『対日不信』」という記事を書いています。
日本の政治家たちがいきり立てばいきり立つほど、実は、日米同盟にもひびが入るという外交的マイナスになっていることに、彼らは思い至っているのでしょうかねえ。こういう大事な記事を紙面に載せなかった「日経」も根性なしです。^^;
会員限定記事ですが、一読の価値ありです。
です・ます調『資本論』
ちょっと思いつきで、『資本論』をです・ます調で訳してみました。やってみると、ただ文末を「です」「ます」に置き換えたというだけではなく、全体がなんだかソフトになったような気がして、文章そのものもそれに相応しく平易にしなければなりません。長い、くだくだしい、いかにも翻訳文といった感じの文章から脱却するのには、ちょうどいいかも知れません。^^;
なんと大胆な! 宮地正人『幕末維新変革史』上
金曜日、仕事帰りに書店で見つけた本。元国立歴史民俗博物館館長の宮地正人氏の新刊書ですが、帯の宣伝文句がすごい!
激動の歴史過程を一貫した視点から描く、幕末維新通史の決定版
「決定版」と自ら銘打つなんて、こんな大胆なことは宮地先生でなきゃできませんね。^^;
ということで、早速読んでおります。
「ラ・ボエーム」
1日、友人がオペラに出演するというので、夕方から川口へ。
演目は、プッチーニの「ラ・ボエーム」。友人は浮気な女性ムゼッタ役。本人は、自分はキャラ的にはミミだと思っているのかも知れないけれど、なかなかはまってました。^^;
「原発ゼロにする」43%だが、ゼロにするのは「無理」77%
昨日、興味深い世論調査が2つ新聞に出ていた。
1つは「日本経済新聞」の世論調査で、2030年時点での国内総発電量に占める原子力の割合について、政府が示している3つの選択肢について聞いたところ、「原発をゼロにする」が43%でトップだった。
もう1つは、ネットでは見つからないのだが、「産経新聞」の「今週の世論調査から」。ここでは、「2030年代前半までに原発ゼロを実現できると思うか」との質問に、「できると思う」20.2%、「できないと思う」76.8%、だっという。
2030年までに「原発をゼロにすべきだ」という意見が4割を占める一方で、8割近くが「原発ゼロはできないと思う」と回答しているわけで、単純に合計すれば10割を超える。ということは、少なくとも2割の人は、あるいはそれ以上の人が「原発はゼロにすべきだが、ゼロにはできないだろう」と思っている、ということになる。
湘南方面で綱領学習会
今日は、湘南方面に出かけて、綱領学習会で講師を務めました。しかし、2時間のお約束が30分以上オーバー。申し訳ありませんでした。
あの日経ビジネスがこんな記事を…
今日、ツイッター上でも話題になっていた『日経ビジネス』の記事。オンライン版だけの記事のようですが、非正規雇用の増大は何十年後かに必ず生活保護の増加となって跳ね返ってくる、非正規雇用の拡大で大企業の目先の業績だけ良くしておいて、ツケを将来に回すものだと、なかなか手厳しい批判。
さらには、高額所得者や資産家からもっと税金を取るべきだ、この20年優遇しすぎた、20年前の税制に戻せば税収は概算でも今の倍になる、等々。日本は法人税が高いと言われているが抜け穴が多く、実効税率は非常に低い、輸出中心の大企業は20%を切ることが多い、とも。なかなかの論戦です。
本日のお買い物
本日のお買い物
日本の外交をどうするのか
日韓関係がにわかに行き詰まってしまったことから、日本の外交についてつぶやきました。
実は回答したのは135団体のうち33団体のみ
日本経済新聞が報じた、政府の示した2030年時点での原発依存度0%、15%、20〜25%という選択肢について、産業界では0%や15%を師事するところはなく、最低でも20〜25%、あるいはもっとそれ以上ないと生産や雇用に大打撃を受ける、という記事↓。
実はもとになっているのは、日本経団連が13日に発表したこちらのアンケート↓。(PDFファイルが開きます)
で、これを読んでみると、まず驚いたのは、アンケートを送付したのは135団体で、回答を寄せたのはわずか33団体しかなかったという事実。産業界あげて0%や15%ではとんでもないことになると言っているのかと思いきや、実は、それは一部のことだったのです。
しかも、中身を見ていくと、アンケートそのものに慶応大学・野村准教授による生産と雇用への「影響分析」なる資料がつけられていて、要するに、原発依存度が0%、15%だとこんなに大変なことになると予測されているが、お前のところの業界は大丈夫か? という調査になっているのです。
室内楽が楽しくなってきました
8月はオーケストラも夏休みということで、生オケを聞く機会も少なくなります。ヨーロッパでは、みんなバカンスに出かけてしまうので、都会でコンサートをやってもそもそも来るべき客がいないということなんでしょうが、日本では、夏休みで時間のあるときこそコンサートに通うチャンスじゃないかと思うんですが…。
しかし、そんなことをぼやいていても仕方ないので、4日、5日と都響関係のコンサートに通ってきました。
まず4日は、サントリーホールで開かれたプロムナードコンサート。プログラムは以下の通り。
イギリスとイングランド
『資本論』を読んでいて、気になるのは、「イギリス」という言葉。地名としては「イギリス」という言葉は英語にもドイツ語にもありません(現在のイギリス国の正式な名称は「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」)。邦訳を原書とつき合わせてみると、イギリスはEnglandあるいはenglischの訳語としてだけでなく、さらにbritisch(ブリティッシュ)の訳語としても用いられています。他方で、「連合王国」や「ブリテン」も出てきて、うむむ…
そう思って読んでいると、第23章第5節「資本主義的蓄積の一般的法則の例証」の原注(107)で、マルクス自身が次のように書いていました。