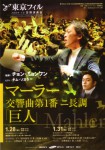前項の続き。
上製版843ページ3-4行目(新書版846ページ左から3行目)に出てくる「産業調査委員会」が、「児童労働調査委員会」のことであることは、前回指摘したとおり。
これに刺激されて、ほかにもいろいろ登場する「委員会」について調べてみました。
たとえば、その直後には、「1840年に児童労働にかんする調査のための議会委員会が任命されていた」(新書版846ページ最終行)と出てきます。
さらに、次のページ(フランス語版から第4版に取り入れられた部分)には、こんな記述も出てきます。
議会は、1863年の委員会の諸要求を、かつての1842年の要求のようにあえて拒絶しようとはしなかった。
さらに、数行後にはこんな記述も。
1867年2月5日の開院式の勅語のなかで、当時のトーリー党内閣は、その間1866年にその仕事を完了していた委員会の最終提案にもとづいて、さらに別の諸法案を発表した。
さらに、新書版851ページには、「1862年の調査委員会」「1840年の調査委員会」というのが出てきます。
これらの「委員会」は、何の委員会なのか? いったいイギリスにはいくつ委員会があるのでしょうか?
いろいろ調べてみると、イギリスでは「児童労働調査委員会」とか「工場調査委員会」といわれるものは3次にわたってつくられていたことが分かりました。正式名称などは、いまいち確認しきれませんでしたが、いちおう以下のとおりです。
- 第1次は、1833年につくられた「工場児童雇用調査委員会」。33年、34年に報告書を下院に提出しました。
- 第2次は、1840年に組織された「鉱山および炭坑、ならびに商工業における児童および青少年の雇用にかんする調査委員会」。これは1840年の下院の議決にもとづきつくられた委員会で、だからマルクスは「議会委員会」と書いているわけです。この委員会は、1842年に第1次報告を、1843年に第2次報告を提出。第1次報告が鉱山労働にかんする調査報告で、マルクスが「1842年の要求」といっているのはこの報告書のことです。エンゲルスが『イギリスにおける労働者階級の状態』で、この委員会の報告を活用しています。
- 第3次が、「児童労働調査委員会」(正式名称は「工場法未適用職業・製造業、すなわち、陶器、黄燐マッチ、ファスティアン織裁断、レース・メリヤス機械、煙突掃除における児童労働にかんする委員会」?)で、1862年に組織され、1863年から66年まで、5次にわたる報告書を発表。これが『資本論』で一番多く引用されている「児童労働調査報告」です。先ほどマルクスが「1863年の委員会」とか「その間1866年にその仕事を完了していた委員会」といっていたのは、この委員会のことです。
いずれの委員会も「工場調査委員会」あるいは「児童雇用調査委員会」などと略称されることあったので、マルクスは、「現在の調査委員会」とか「1840年の委員会」とか呼んでいる訳です。
ここまで調べて、はじめて意味がわかったのが、第7章「剰余価値率」第3節「シーニアの『最後の一時間』」の原注(32)に出てくる、次の文章。
レナド・ホーナーは、1833年の工場調査委員の一人であり、1859年までは工場監督官、実際上の工場監察官であって、彼は、イギリスの労働者階級のための不滅の功績をたてた。
現在は、この「監察官」というのにだけ訳注がついていますが、実は、ここの「1833年の工場調査委員」というのは、上で説明した第1次の「工場児童雇用調査委員会」のことだったのです。
レナド・ホーナーは、1833年に初めて工場監督官制度がつくられたときから工場監督官として労働者の権利を守ってたたかった人物として有名ですが、実は、その前に、1833年に「工場児童雇用調査委員会」がつくられたときに委員の1人に任命されて、このときから労働者の権利を守るためにがんばっていたのです。これについては、Leonard Horner – Wikipedia, the free encyclopediaをご参照ください。
なお、『資本論』では「児童労働調査委員会」という翻訳が定着していますが、英語ではChildren’s Employment Commissionなので、「児童雇用調査委員会」という方が正確ではないかと思います。『資本論草稿集』では、第2次の委員会について「児童雇用調査委員会」という訳語をあてています。また、『イギリスにおける労働者階級の状態』では、大月書店『全集』版でも、新日本出版社・古典選書シリーズ(浜林正夫訳)でも、「児童雇用調査委員会」と訳されています。
Related Articles: