
 |
福島清彦氏は、野村総研主任エコノミスト。なぜアメリカは、国際社会の反対を押し切って、一方的なイラク攻撃を強行したのか。それを、アメリカという国の建国以来の独特な伝統に遡って考えています。そして、「自由を世界にひろめる」というアメリカの「特異で独善的な使命感」を問題にします。福島氏は、前著『ヨーロッパ型資本主義』では、市場万能アメリカとは違う、ヨーロッパの“人間の顔をした”資本主義をとりあげていましたが、今回の著作は、それをベースに、イラク戦争を前にそのヨーロッパと対立したアメリカの姿を描いています。
ブッシュ・ドクトリンの結末として福島氏は、(1)ベトナム戦争のように泥沼化する、(2)テロ組織の破壊などの目標はある程度達成しても、アメリカは国際的に孤立化し影響力を低下させる、(3)テロ支援政権の打倒を手始めに中東諸国の“改造”にある程度成功する、(4)中東地域の諸国民に歓迎され、“逆ドミノ”式に民主的平和的親米政権の樹立に成功する、という4つのシナリオをあげていますが、もちろん氏の予測は(2)あるいは最悪の場合は(1)になるというものです。
第4章では、イスラム諸国の「自己改革」の動きが紹介されています。これがどこまで現実の動きなのかは私には分かりませんが、他にはあまり紹介されないものだけに、こうした動きにも注目する必要があると思いました。また、ブッシュ戦略の行方を決める1つの要素として、「ジャパン・マネー」の役割が指摘されています。しかし、ドルべったりの外為政策から離脱したかたちで、アジア独自の国際通貨基金づくりがすすむかどうか、対米追従の自民党政権にそれが実行できるとは思えませんが、しかし、体制的矛盾の深まる方向として注目されます。
 |
いまごろ・・・と言われそうですが、『OUT』を読みました。正直いって、『グロテスク』以上に気味悪く思いました。というのも、『OUT』に描かれている世界が、イヤになるほど身近な世界だからです。武蔵村山とか小平の何とか団地とか、そういう場所が非常に身近だということもありますが、それ以上に、登場する4人の主婦たちの暮らしぶりが、あまりにありふれた、どこにでもある普通の暮らしに思えたからです。普通の生活のなかで、普通に芽生える“殺意”。考えただけでもぞっとします。
それから、ミステリーとしても、『OUT』はなかなか良くできていますね(こういう言い方も変だけれども)。途中で、若い刑事が4人のところを順に訪れて、それぞれの生活をのぞき込んでいったところや、佐藤=佐竹が雅子に迫っていくところなどは、思わずハラハラして引き込まれてしまいました。しかも、刑事が事件の真相を解き明かすのなら普通のミステリーだけれども、そうならないところが、桐野夏生のおもしろさなのかも知れません。『グロテスク』から遡って読み返してみると、『OUT』も、ある意味、4人の主婦たちや佐竹などの主観の世界を重ね合わせてつくりあげられているし、普通のミステリーの枠には全然収まっていないし、共通するところにたくさん気づかされました。
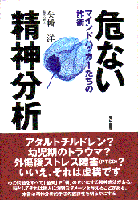 |
1990年代、アメリカでは、セラピーを通じて「実は子どもの頃、私は親に性的虐待を受けていた」といった“抑圧された記憶”がよみがえったとして、もうとっくに大人になった子どもが親を訴えるという裁判が多数起こされました。しかし、こうした訴訟は、やがて、そうした“記憶”そのものが実はセラピストたちによって植え付けられた“偽りの記憶”だったということが明らかにされ、いまでは、逆にそのセラピストたちが親たちによって訴えられるようになっています。
と、ここまでなら僕もく何となく知っていました。しかし、そうしたセラピストの親玉が、『心的外傷と回復』の著者ジュディス・ルイス・ハーマンだったというのは、この本を読むまで知りませんでした。ハーマンは、PTSD(外傷後ストレス障害)の権威といわれる人物で、阪神大震災いらい、日本でもPTSDが注目され、ハーマンの『心的外傷と回復』も読まれてきたそうです。
しかし、そもそも、何か心的外傷がストレスになって、そのときの“記憶”がそっくりそのまま心のどこかに封じ込められていて、しかも、その記憶が大人になってから蘇ったりするものなのか? そういう精神医学の根本的な問題は、案外検討されてきませんでした。しかも、軽い不安定愁訴だったクライアントの多くが、セラピストから「あなたは性的虐待を受けていたのではありませんか?」「それを認めないかぎり、あなたの病気は治らない」と言われ、“偽りの記憶”を呼び覚ましてしまったばっかりに、かえって症状を悪化させてしまった事例ばかりだというのです。そのために、アメリカの精神医学会は「記憶回復療法」を適正な治療法から除外したというのです。著者は、こうした事実をあげて、「記憶回復療法」によるセラピストを「マインド・ハッカー」と呼んで告発します。
もちろん、著者も、阪神大震災のような大きな災害や事件・事故などの場合に、さまざまなストレス症状が出ることは認めています。しかし、PTSDは、予防医学的には有効な概念ではあっても、何でもかんでもPTSDとすることには明確に反対し、異議を唱えています。さらに筆者は、PTSDだ、アダルト・チルドレンだと、何でも“心の問題”にし、子どもの頃の親の育て方の問題にしようとする現代の傾向にも警鐘を鳴らしています。最近も、少年事犯が起こるたびに、母親の愛情が足りなかったのではないかといった論評が新聞に登場しますが、母親の愛情が足りなかった子どもがみんな殺人を犯す訳ではないのだから、これは何も説明していないという指摘は至極まっとうなお話です。
日本人はとかく依存的で、他人から「あなたは**だ」と言われたがる。しかし、自分の人生を変えることができるのは自分だけ。自分の人生の「不幸」を何かのせい、誰かのせいにするのはやめよう、というのが著者の結論です。自分はどうしてこんなに不幸なのかと悩んでいる人は、ぜひ一度読んでほしいと思います。
 |
本書に登場するのは、IBM、インテル、あるいはバンカメなど、アメリカの一流企業に働くホワイトカラーの人たち。彼ら・彼女らは、朝7時から12時間以上も働き、その上、交代で24/7(7日間、24時間いつでも呼び出しに答える)のシフトをこなし、週末も携帯やノートパソコン、PDAなどでいつでも仕事のメールチェックをする。そういう彼ら・彼女らの働きぶりを、当事者たちに取材して書かれている。
そこで紹介されているアメリカのホワイトカラーの職場の状況は、1980年代から90年代にかけて、M&Aやリエンジニアリングを繰り返すたびに、ひどくなっている。同僚の数は減り、仕事は増え、しかも給与は上がらず、社員の福利厚生は減る。アメリカの場合、医療保険などは企業が負担するので、福利厚生の削減というと、真っ先にあがるのは医療保険の切り下げと企業年金・退職金の削減。これを著者は「ホワイトカラーの奴隷工場」と表現する。
読んでいると、日本の姿と重なってくる。しかし、たとえば著者は、全労働者の8.5%が週60時間以上働いているとして問題にしているが、日本では、週35時間以上働く労働者(男性)の20%が週60時間以上働いている。しかもこの比率は、従業員500人以上の事業所について見れば、1994年の14.1%から2002年の21.2%へと急激に増えている。だから、事態は日本の方が深刻なのだ。医療保険だって、日本の場合は公的な皆保険制度になっているので会社が社員の医療保険を切り下げるということはないが、健康保険の保険料の値上げと本人窓口負担の引き上げのほかに、たとえばパートや派遣労働者のある部分は健康保険から排除されている。
だからこの本は、「へえ、アメリカって大変なんだ〜」というのではなく、リストラを続ければ、日本だって、同じような事態になるという警告になっていると思う。
もう一つ。著者は、たとえば1980年代から1990年代半ばに行われた企業合併の65〜75%が金融的に破綻し、株主価値で大きな損失を出しているという事実を紹介している。実は、企業合併とリストラをやりさえすれば、株価は上がり、企業収益は上昇するといった“経営哲学”は実際にはまったく裏付けられない、たんなる“信仰”にすぎないということだ。むしろ職場の安定こそが企業の安定した発展をもたらすと著者は強調している。「改革なくして、景気回復なし」とか「規制緩和」を何とかの一つ覚えのように繰り返す小泉首相や竹中平蔵大臣には、ぜひとも感想を聞いてみたい。
 |
桐野夏生にはまってしまった。この小説も『グロテスク』と同じように主人公の少女たちの“語り”で話が展開する。主観的な世界を重ね合わせることによって、現実の世界を描いていくというその手法は、『グロテスク』ではさらに磨きがかかっている。
4人の少女たちは、大人たちとはちょっとずれた自分たちの世界を必死に守ろうとする。しかし、その4人たちも、一人一人、他の子には言えない自分の世界を必死で守っている。それが、彼女たちの“リアルワールド”なのだろうか? しかし、結末では、事件への自分のかかわりから、親友の二人が事故死、自殺をとげたことにたいして、主人公の女の子が、彼女らの死を「うけとめ」て生きていくと決意している。そうやって、彼女は、自分たちの世界から現実の世界へと旅立っていくのだろう。作者のいいたい“リアルワールド”というのは、この現実の世界への立ち帰りなのかも知れない。
なぜ、海流や気流が生まれるのか。なぜ、黒潮とかメキシコ湾流とか、強い海流は大洋の西岸側にだけあるのか。川のように、水が高いところから低いところへ流れるというのは分かるが、同じ高さであるはずの海で、どうして海流が流れ続けることができるのか・・・・などなど、海流や気流の「不思議」が明らかにされる。エルニーニョ現象の仕組みとか、北大西洋から潜り込んで南氷洋、インド洋、南太平洋から北太平洋へと1000年もかけて流れる深層海流の仕組みとそれが気候にあたえる影響とか、面白い話題がいっぱい。
著者は、読売新聞の科学部の記者。東大大学院物理学科博士課程で海洋物理学を専攻していたというだけあって、中身は確かなものだし、さらに記者らしく、素人に分かりやすく、非常に基本的なところから説明している。「コリオリの力」なども分かりやすく説明されていて、気軽に読めるようになっている。
この本でとくに興味深く思ったのは、最後の章が「社会と科学のかかわり方」になっていること。この場合、科学というのは自然科学のことだが、地球温暖化とか異常気象といった現象は科学の目でとらえる必要があるということ、それに、地球温暖化現象のように、科学ではまだすべて解明されていない問題についても、社会は対応をせまられる場合がある、だから、必要なことは科学の結論を鵜呑みにすることではなく、そういう結論がどうやって導かれてきたか、その過程をきちんと理解することが必要だということが強調されている。
著者は、1963年神戸生まれというから僕より少し年下。自称・女子供文化評論家として、女子中学生、女子高生の動きを雑貨とか洋服とかの流行をつうじて追っかけたり、マンガ、タカラヅカなどなどのコラムを書いてきたらしい。いわゆるサブカル系の評論家。
最初に映画「バトルロワイアル」がとりあげられているけれども、面白いのは、BR法というのが決まったからといって、どうして素直に、生徒同士で殺し合いを始めるのか、という根本的な疑問を呈していること。この映画を反社会的だなどと批判した政治家がいたけれども、それどころか「決まっちゃったんだから、しかたないじゃん」といって、殺し合いを始めるんだから、本当は体制順応育成の映画ではないか、というのだ。あと、浅田次郎の『鉄道員』や『天国までの百マイル』なんかで泣いちゃいけないという話とか、笑える話がいっぱいある。途中に、タカラヅカのベルバラの話とか、ガンダムの名台詞とかも出てきて、さすがサブカルなどと妙な感心もしてしまう。
でも、この本がすごいのは、そういうカルトな話で終わらないというところ。著者の結論はと言うと、
などなど。文章はサブカル調で、軽いノリで、世間にいろいろツッコミを入れているという感じだけれど、結論は非常にまともで、真面目なものだと思う。
前著『豊かさとは何か』(岩波新書)は、バブル華やかなりし頃に、見かけの“豊かさ”にたいして、本当の豊かさとは何かを問いかけて話題になった。こんどは、デフレ不況が長期化するもとで、本当に豊かな社会をつくるためには何が必要かを問いかている。小泉首相がおしすすめる「構造改革」が掲げる“市場経済、競争万能”とは違う、「もう一つ」の社会のあり方を探求している。
まず著者は、失業、非正規労働、長時間労働など「切り裂かれる労働と生活の世界」に目を向け、“社会を支える労働者がそんなに不安定、無権利でいいのか”と問いかける。そして、子どもたちの世界に目を転じると、労働者を切り裂いているのと同じ「無限の競争の歯車」が子どもたちを押しつぶしていると、厳しい告発。それにたいし、阪神大震災のボランティア活動やボスニア支援のNPO活動に、著者自ら、学生や若者を引き連れて飛び込んでいくと、そのなかから学生や子どもたちが生きいきと生まれ変わっていくすがたが描かれる。このあたりは、暉峻さんの驚くべきエネルギーに圧倒される。
そして、そういう実例を通じて、著者は、私たちの社会が「共有化された互助的な社会的共有部分」によっても支えられていることを明らかにする。そして、競争原理とは質的にちがう、この互助的な「もう一つ」の原理によってこそ、豊かな社会はつくりあげられると訴えている。
 |
少し前の日曜日の新聞の書評欄に同時に2紙に載っていたので、さぞかし話題になっているんだろうと思って、とりあえず買ってきて、5日間で読んでしまった。上下2段組なので、結構な分量がある上に、「わたし」の語りで話が進むというスタイルなので、最初は取っつきにくかったけれども、はまると、逆に抜け出せなくなるこわ〜い世界。
東電OL殺人事件に題材をとっているけれど、別に、あの事件の真相を解明している訳ではない。なぜ一流企業のOLが街娼をやっていたのか、その内面を桐野夏生さんなりに描いてみたという感じ。本人も、毎日新聞のインタビューで、登場人物をちょっとデフォルメしたと言っていたけれども、読んでいると、実際、いそうだなあと思わせるようなキャラクターが、だんだん歪んでいって、おかしくなっていく感じが不気味で、現代社会の怖さを感じさる。
でも最後は、行くところまで行ってしまうという感じで、ストーリー的にも登場人物自身も破滅に向かってしまい、答えとか解決とか救済とかいうものはどこにも出てこない。そういう意味で、ほんとにグロテスクな話。こんなのホントに読む人、いるんだろうか?
※某紙にコラムを書きました。
そもそも、第二次大戦の戦勝国で、日本の植民地支配から「解放」されたはずの朝鮮が、その後、南北分断と同じ民族同士による内戦、そして独裁政権に苦しむことになり、あべこべに「敗戦国」日本は朝鮮戦争の「特需」と日米安保で繁栄を謳歌する。こういう「歴史の逆転」を忘れた(あるいはわざと無視した)まま、北朝鮮を「悪の権化」と決めつけ、嘲笑の対象とさえし、制裁を振りかざす論調にたいする著者の厳しい批判が印象的。
さらに、日朝関係、日韓関係、米日・米韓・米朝関係を1945年の日本敗戦からふり返りながら、「あるがままの北朝鮮」を認めつつ、対話による解決の道を探らなければならない理由を明らかにしている。また、なぜ北朝鮮が、「拉致」を認めるなどまでして日朝交渉にかけたのか、日朝平壌宣言が東北アジア地域の平和と安定にどのような可能性を開いたのかを、冷静に論じている。
マスコミでのある種「言いたい放題」現象が起こっているなかで、勇気ある一書といえる。
 |
識字率と出産率(いわゆる「合計特殊出生率」)の変化で「文明化」の度合いを測るというのは、なかなか奇抜なアイデアだが、それを読みながら、以前、日本経済史の中村政則氏が「2000ドル」理論というのを展開していたのを思い出した。国民一人当たりGDPが2000ドルを超えると、いわゆる「市民社会」状況が生まれ、開発独裁も民主化へ向かわざるをえないという「理論」で、当時は「近代化」論の焼き直しだとか、無思想・無内容とさんざんだったが、現象的にいえば、トッドの識字率・出生率と同じで、確かに、それらの数値がある経験的な値を越えると、社会的な変化というものが現れる。いずれにしても、最奥部での経済的変化を反映したものであることは間違いなく、単純な「土台還元」論よりは面白いかも知れない。
トッドの議論でもう一つ面白いのは、婚姻形態や家族形態、それらとむすびついた財産相続の形態などをつなぎあわせけて、社会の質――普遍主義か差異主義か――をとりあげ、それを資本主義の類型論に結びつけていること。アメリカの動きを、普遍主義と差異主義という二つの軸から見ていこうという視点は、文化論として興味深い。
しかし、トッドの議論は、まず第一に、日本についてはからきしダメ。彼は、日本をドイツ、あるいはロシアの延長としてしか見ていない。具体的に研究したことはないのではないだろうか。第2に、これは日経の書評で指摘されていたことだけれども、フランスについても全然批判的な視点がない。まあ、彼自身はけっして左翼ではないのだから、これは彼の責任というより、トッドを左翼のように誤解する連中の責任というべきかも知れないが。いずれにしても、トッドの本は、面白くて一気に読ませてくれる。
二〇世紀のと銘うたれているが、明治維新直後から現在までの日本史学史が対象になっている。
戦前は、明治維新直後にブルジョア実証史学が中軸になっていった経過と、それにもとづく実証史学(のちに「国体史観」となる)と、『日本資本主義発達史講座』に代表されるマルクス主義史学、さらに昭和になって台頭する皇国史観の対抗を、歴史学だけでなく京都学派の「世界史の哲学」などもふくめながら概括している。戦後は、マルクス主義歴史学と実証史学、それにアカデミズムの合流として戦後歴史学の大きな流れを明らかにしながら、そのなかで登場したマルクス主義歴史学への批判的な研究動向をきちんと位置づけ、研究対象を広げながら豊富な研究成果を揚げてきたことをていねいに跡づけている。同時に安易な戦後歴史学批判には毅然とした姿勢をつらぬいて、戦後歴史学研究の大きな達成をあらためて明確にすることに努力されている。
永原先生の専門である日本中世史の分野にとどまらず、古代史、天皇制研究、近現代史にまで目を配ってあるところは、さすがというべき。教科書問題や「つくる会」の動向などへの批判という問題意識が鮮明。史学史というものがとても大事なものであることがよく分かる。
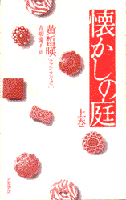 |
1980年の光州事件で逮捕された政治犯の男性を主人公にした小説で、光州事件のときの様子や、そのあと指名手配された活動家たちが潜伏・逃亡したときの様子が、18年ぶりに釈放された主人公の回想という形で描かれている。
黄晢暎は、『客地』という小説が、以前、やはり岩波書店から邦訳されているが、彼自身、民主化闘争のリーダーで、1989年に北朝鮮を訪問し、そのままヨーロッパに脱出し、帰国後、収監されたという経歴を持つ。小説のなかでは、朴正熙政権や全斗煥政権の弾圧のもとで、韓国の活動家たちが、こっそりと『資本論』や『国家の起源』などを洋書や日本語の文献で読んでいたという話なども登場する。韓国の民主化運動、あるいは左翼運動というものが、日本と意外と距離が近いことに今更ながら気がつかされ、テレビに映った光州事件の様子と大学のキャンパスでハンガー・ストライキをやっていた韓国からの留学生のことが思い出される。
小説の内容は、しかしながら、ベルリンの壁の崩壊、ソ連の解体という現実に、著者自身のある種の挫折や諦めに似た気持ちを漂わせるものになっている。もちろん、闘争の放棄ではないが、著者が、あるいは韓国の左翼自体が新しい方向を模索している様子をうかがわせる。
それにしても、ちょうどワールドカップで韓国中が「テーハミングッ」の歓声にわいているときに、20年後にはそんな社会になっているとはまったく想像もできなかったような厳しい時代をふり返った小説を読むというのは、一種独特の感慨がわく。
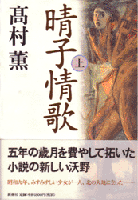 |
これは、1970年頃の東北を舞台にした小説。主人公は、遠洋漁業の漁船に乗っている船員で、船のなかで、主人公の母親が、母親の両親(主人公からみれば祖父母)の若い時代ころをふり返る手紙を書いてよこすのを読みながら、母親のことや自分の若いころのことを回想するという、二重、三重に積み重なっている。
本書のテーマはいろいろある。しかし、1930年代の徐々に暗転していく日本の時代状況が、その後の結末を体験し知っている人間(母親)の目を通して回想され、描かれていくところに、この本の魅力の一つがあると思う。戦前の日本社会の描写には、有事法制などの整備が進められようとしているいまの時代にたいする作者の気持ちが色濃く映し出されている。
| << BACK |